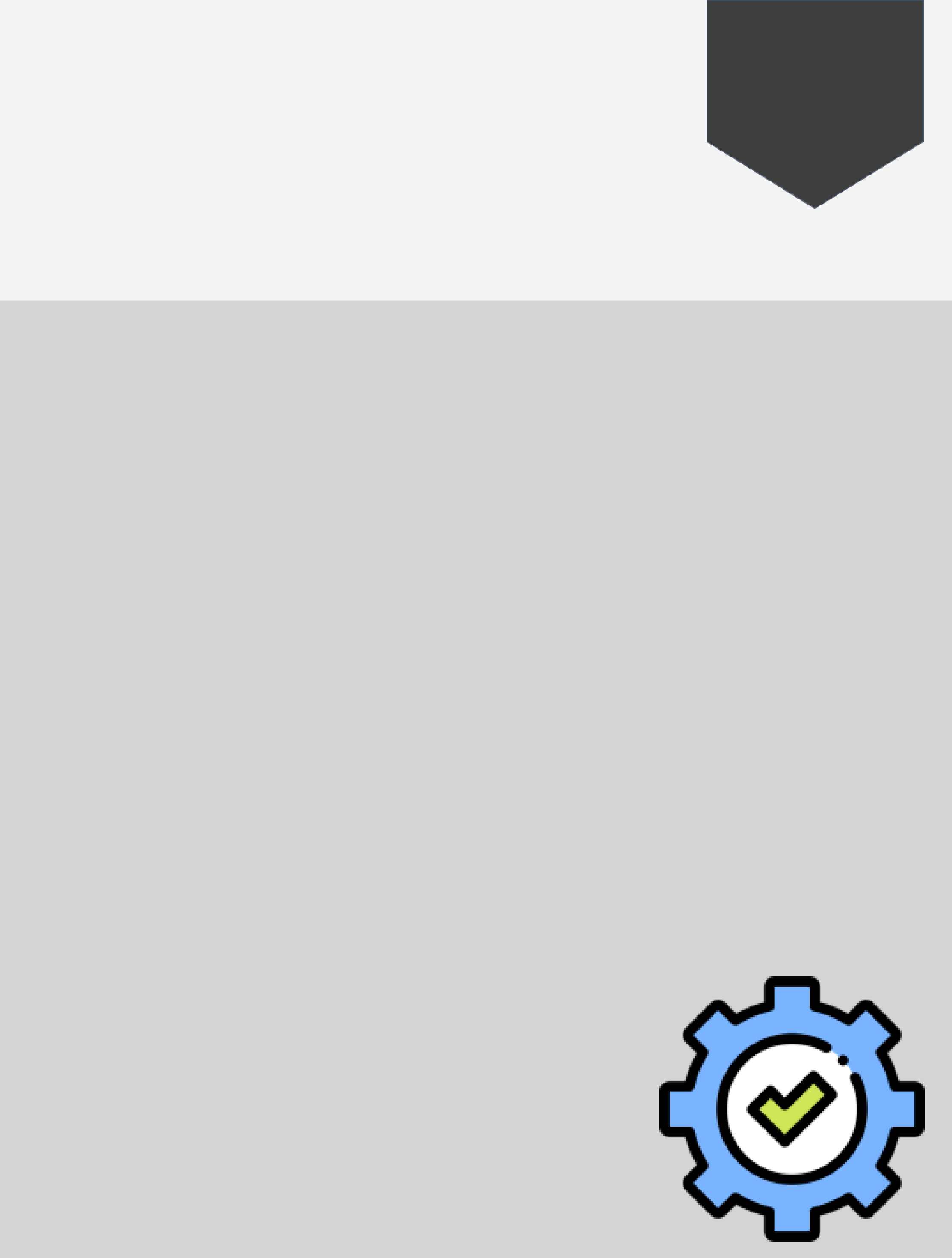$$\newcommand{A}[0]{\mathbb{A}}
\newcommand{AA}[0]{\mathscr{A}}
\newcommand{abs}[1]{\left\lvert#1\right\rvert}
\newcommand{Arg}[0]{\operatorname{Arg}}
\newcommand{BB}[0]{\mathscr{B}}
\newcommand{C}[0]{\mathbb{C}}
\newcommand{CC}[0]{\mathscr{C}}
\newcommand{F}[0]{\mathbb{F}}
\newcommand{floor}[1]{\left\lfloor#1\right\rfloor}
\newcommand{ind}[0]{\operatorname{ind}}
\newcommand{K}[0]{\mathbb{K}}
\newcommand{Ker}[0]{\operatorname{Ker}}
\newcommand{L}[0]{\mathbb{L}}
\newcommand{mmod}[1]{\ \left(\mathrm{mod}\ #1\right)}
\newcommand{Mod}[1]{\ \left(\mathrm{mod}\ #1\right)}
\newcommand{N}[0]{\mathbb{N}}
\newcommand{ord}[0]{\operatorname{ord}}
\newcommand{Q}[0]{\mathbb{Q}}
\newcommand{R}[0]{\mathbb{R}}
\newcommand{rank}[0]{\mathrm{rank}}
\newcommand{SS}[0]{\mathscr{S}}
\newcommand{TT}[0]{\mathscr{T}}
\newcommand{UU}[0]{\mathscr{U}}
\newcommand{wenvert}[1]{\left\lvert\left\lvert#1\right\rvert\right\rvert}
\newcommand{Z}[0]{\mathbb{Z}}
$$
$F\in \K[X, Y]$ を $n$ 次多項式とし、曲線 $C=V(F)$ 上の点 $P=(a, b)\in C$ をとる。このとき、正の整数 $m\geq 1$ が存在し、$i=m, \ldots ,n$ に対して、$i$ 次の$2$変数斉次多項式 $F_i (X, Y)$ をうまくとれば
$$F(X+a, Y+b)=F_m(X, Y)+\cdots +F_n(X, Y)$$
となる。実際、左辺は $(X, Y)=(0, 0)$ のとき $F(a, b)=0$ となるから、左辺は定数項が $0$ の $n$ 次多項式となる。
このような $m$ で最大のものをとると $F_m(X, Y)\neq 0$ となる。このとき $m$ を $C$ の点 $P$ における重複度 (multiplicity) といい、
$m_P(F)$ であらわす。また点$P$ の重複度が $m$ のとき、この点を $m$ 重点という。
$1$ 重点、つまり $m_P(F)=1$ となる点 $P$ を非特異点 (nonsingular point) あるいは単純点 (simple point) という。$m_P(F)>1$ となる点 $P$ を特異点 (singular point) という。特異点をもたない曲線を非特異曲線 (nonsingular curve) あるいは滑らかな曲線 (smooth curve) という。
$$Y^2=X^3+X^2$$
で定義される曲線、つまり
$$V(Y^2-X^3-X^2)$$
は原点を特異点にもち、原点は $2$ 重点となる。
$n$ 次の$2$変数斉次多項式の偏導関数は $n-1$ 次の$2$変数斉次多項式となることから、次のことがすぐにわかる。
点 $P(a, b)$ が曲線 $C=V(F)$ の特異点 $\Longleftrightarrow$ $F(a, b)=F_X(a, b)=F_Y(a,b)=0$.